累計発行部数が1100万部(2024年8月の公表)というメガヒット級のライトノベル『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』。小説投稿サイト「小説家になろう」で2013年9月から連載スタート、2017年3月に全5部677話で完結しましたが、2017年4月から番外編『本好きの下剋上 ハンネローレの貴族院五年生』が始まっています。
メディアミックスも盛んで、漫画やアニメ、ドラマCD、関連グッズなど多岐にわたって展開されています。
多くの人に読まれている作品にありがちなことですが、「本好きの下剋上」の主人公であるマインに対する読者の評価は大きく分かれています。彼女を好きな読者と嫌いな読者が存在する時点で、いかに多くの人に作品が読まれているかを表しているようなものですが、「本好きの下剋上」のすごいところは”マインが嫌いでも作品は好き”という読者も多いという点です。
今回は主人公・マインの評価を中心に、『本好きの下剋上』の魅力について掘り下げていきたいと思います。
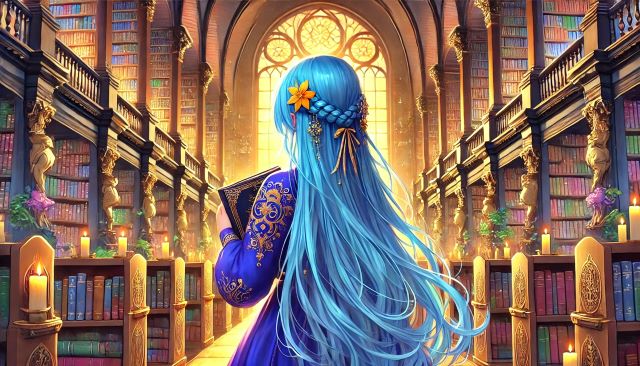
もくじ
マインの好きなところ、魅力的な点
マインの良い点・好きな点を拾い出してみましょう。
◇本を読むことが生きがいだった前世の記憶を持ち、異世界に転生して本がほとんど存在しない状況に絶望しますが、「本がないなら作ればいい」と決意し奮闘します。
◇本を作るためなら手段を選ばないという強い意志と行動力が描かれています。この本づくりへの異常な執着が、物語を動かす原動力の一つとなっています。
◇女子大生だった前世の知識を頼りに、紙やインクなどの物作りに挑戦し、成功させていきます。
◇パンケーキや髪飾りなどの品物を作り、商人のベンノと契約してビジネスに繋げるなど、その才覚を発揮します。
◇常識に囚われない発想で、大人をも圧倒する交渉を見せる爽快さがあります。
◇周りを巻き込みながら目的に近づいていく姿が描かれています。
◇中身は成人女性ですが、病弱な幼い体で転生したマインは周囲の人々の助けを得なければいけない存在で、守ってあげたくなります。
◇当初は本への執着が強かったですが、家族や周囲の人々との関わりの中で、大切なものを守りたいという気持ちが芽生え、人間的に成長していく姿が魅力的です。
◇病弱で小柄な体格、紺色の髪に金色の瞳という外見が可愛らしい。
◇笑顔やふくれっ面など、表情が豊かで、ルッツやフェルディナンドとのやり取りで見せる様々な表情が可愛らしい。特にアニメ化によって、その仕草や動きの可愛らしさが伝わりやすくなりました。
◇マインを支え、影響を与える家族や友人、商人、神官長など、個性豊かで魅力的なサブキャラクターが多いことも、作品全体の面白さに繋がり、マインの魅力をより引き立てています。
主人公・マインに好意的な読者の評価
マインのことが好きな読者の視点は次のように整理できそうです。
成長と努力の姿勢
マインは異世界で本を作るために奮闘する姿が描かれており、その努力や行動力を評価する読者が多いです。彼女の情熱や目標に向かう姿勢は、特に「本好き」の読者にとって共感を呼ぶ要素となっています。
転生ものには”主人公がチート山盛り”という設定に走りがちですが、マインは転生した時から虚弱体質で謎の熱病(身食い)を持ち、苦労しながら成長していきます。とんとん拍子に行かないところに読者は引き込まれます。
キャラクターの魅力
マインの独特な性格や、時には自己中心的な行動が物語に深みを与えていると感じる読者もいます。ストーリーを通して彼女の成長過程や、周囲との関係性の変化を楽しむことができるため、物語全体に対する愛着が強まります。
ファンタジー要素の楽しさ
異世界での冒険や魔法、社会制度の描写が魅力的であり、マインの行動がその世界観を引き立てると感じる読者もいます。特に、彼女が本を通じて社会に影響を与える様子は、ファンタジー作品としての楽しさを提供しています。
マインの嫌いなところ、欠点
マインの嫌いなところ、苦手と感じる点を拾い出してみましょう。なお、物語の初期設定として、主人公の性格が「最悪」であると作者自身が注意書きで述べています。
◇特に本が絡むと周りが見えなくなり、欲望のために突っ走る自己中心的な言動が多く見られます。
◇物語の序盤は特に、病弱で貧しい家庭状況にも関わらず自分の欲求を満たすためにわがままを言ったり、家の手伝いを嫌がったりする点が悪目立ちしています。
◇巻が進むにつれて自己中心的な部分が増していくような気がします。
◇見た目は5歳の子供ですが、中身は22歳の成人女性であるため、その言動に違和感や不快感を覚えます。
◇都合が悪くなると子供らしく振る舞うように見える点や、家族を利用しているように感じられる点が鼻につきます。
◇現代日本の常識で行動するため、異世界の文化や習慣を理解せず、常識外れな言動をとることがあります。
◇病弱で一人では生きられない子供でありながら、異世界に対して偉そうに物申したり、周囲に迷惑をかけたりする点が目につきます。
◇特に物語の序盤において、前世や今世の家族に対する感謝や情の描写が少なく、本への執着ばかりが目立つため、人間的な情性が欠けているように見えます。
◇読書好きな設定にも関わらず、本から学びを得たような行動が見られない点や、人の気持ちを推し量る場面が少ない点も、設定との矛盾を感じます。
◇「本好きの下剋上」というタイトルから、本をゼロから作り、普及させていく物語を期待していた読者にとって、途中で図書館の本を読むことや地位を得ることへ目的がシフトしていく展開が「タイトルへの期待と裏切り」に感じられることがあります。
◇物作りでの地道な努力から、唐突に強力な魔力によって物事が解決する展開が増える点に違和感を覚えます。
主人公・マインに否定的な読者の評価
マインのことが苦手・嫌いと感じる読者の視点は次のように整理できそうです。
自己中心的な性格
マインの性格や行動を「わがまま」「自己中心的」と感じる読者が多いようです。周囲に対して配慮が欠けていると思われる場面が少なからずあり、考えなしの行動・無鉄砲・情緒不安定は毎度のこと。これらのことから彼女の行動を不快に感じる読者が多いようです。
精神年齢の不一致
マインは幼い外見に対して、前世の記憶を持つ大人の思考を持っています。そのため周囲の人々に対してドライに見える瞬間も少なくありません。
その一方で、よく考えずに欲望のままに突き進んでしまうことも多いため、”前世の大人の思考はどこに?”と疑問に思う場面が多々みられます。これは本須麗乃の時からこんな感じだったと思われます。
中身は大人のはずなのに子供っぽく、子供なのになぜか大人ぶって上から目線。このギャップが読者に違和感を与え、彼女の行動が理解しづらいと感じる要因となっています。
物語の不幸要素の薄さ
マインの転生後の環境が比較的恵まれているため、彼女の苦労や成長が「本当に苦しいのか?」という疑問を生むことがあります。このため、彼女の下剋上の過程が感情的に響かないと感じる読者もいます。
もっともこれは、マインが本のことで頭がいっぱいなため、困難を困難と認識していないような面があるのも要因です。
陰謀に巻き込まれたり貴族社会の差別によりひどい目に遭ったりもするのですが、その後トラウマやPTSDになることもなく、後に引きずる様子がありません。頭の中が本のことでいっぱいだからなのでしょうか。
マインに対する評価は、彼女の性格や行動に対する受け取り方によって大きく異なります。好きな読者は彼女の成長や努力を評価し、物語の魅力を楽しむ一方で、嫌いな読者は彼女の自己中心的な性格や精神年齢の不一致に不快感を抱く傾向があります。
マインのキャラクターは読者の価値観や期待に応じて、異なる印象を与える複雑な存在であると言えます。
タイトルと内容の不一致についての意見
『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』のタイトルと内容について、合致していないという意見もあります。
この作品は、異世界で本を作ることを目指す主人公マインの物語ですが、タイトルが示す「司書になるためには手段を選ばない」という部分が、物語の全体像を十分に表現していないと感じる読者もいます。
物語の焦点
タイトルはマインの目標である「司書になること」に焦点を当てていますが、実際の物語は彼女が本を作るために奮闘する過程や、周囲の人々との関係性、社会的な障壁を乗り越えることに重きが置かれています。最終的には魔法の話や社会的地位の話にまで話が広がっていくため、タイトルが物語の全体像を十分に反映していないと感じる読者がいるのはわからなくもありません。
手段の多様性
タイトルにある「手段を選んでいられません」という表現は、マインが様々な方法を駆使して目標を達成しようとする姿勢を示していますが、物語の中では彼女が直面する困難や、他者との協力、時には倫理的なジレンマも描かれています。このような複雑な要素が、タイトルのシンプルさと対比して、読者に不一致感を与える可能性があります。
”転生者マイン”の成長と変化
マインの成長は「本好きの下剋上」の物語全体を通じて重要なテーマであり、彼女のキャラクターは各部ごとに段階的に発展していきます。以下に、第一部から第五部までのマインの成長を分析します。
第一部: 兵士の娘
背景と初期の課題
マインは現代の女子大生から異世界の病弱な少女に転生します。彼女は本が大好きで、本を作ることを決意しますが、虚弱な体と本が存在しない環境に直面します。この部では、彼女の基本的な性格や価値観が形成され、特に「本がないなら自分で作る」という強い意志が示されます。
成長の始まり
マインは自らの知識を活かして、紙作りや本作りに挑戦します。彼女の行動は周囲の人々に影響を与え、少しずつ仲間を増やしていきます。この段階では、彼女の成長は主に自己発見と周囲との関係構築に焦点を当てています。
第二部: 神殿の巫女見習い
新たな役割と責任
マインは青色巫女見習いとして神殿での生活を始めます。この部では、彼女が神殿の中での役割を果たすために必要な知識やスキルを学び、より多くの人々と関わるようになります。彼女の魔力や知識が周囲に認められ、次第に重要な存在となっていきます。
人間関係の深化
マインはフェルディナンドやルッツとの関係を深め、彼らとの信頼関係を築いていきます。この部では、彼女の成長が単なる自己中心的なものから、他者との協力や理解へとシフトしていく様子が描かれています。
第三部: 領主の養女
権力と影響力の拡大
マインは領主の養女として、より大きな権力と責任を持つようになります。この部では、彼女が貴族社会の中でどのように自らの立場を確立し、影響力を持つようになるかが描かれています。彼女は商業活動や教育に関与し、社会に貢献する姿勢を見せます。
内面的な成長
マインは自らの魔力や知識を駆使して、周囲の人々を助けることに喜びを見出します。彼女の成長は、自己実現から他者への奉仕へと進化していきます。
第四部: 貴族院の自称図書委員
知識の深化と社会的地位の確立
貴族院での生活を通じて、マインはさらなる知識を得て、貴族社会の複雑さを理解するようになります。彼女は図書委員としての役割を果たし、図書館の重要性を広める活動を行います。この部では、彼女の知識が社会的な影響力を持つようになり、彼女自身も成長を遂げます。
人間関係の複雑化
マインは新たな仲間や敵と出会い、彼女の人間関係はさらに複雑になります。特に、フェルディナンドとの関係が深まり、彼との信頼関係が彼女の成長に大きな影響を与えます。
第五部: 女神の化身
最終的な成長と自己実現
最終部では、マインはついに自らの目標を達成し、貴族院の中での地位を確立します。彼女は自らの魔力を最大限に活用し、社会における重要な役割を果たすようになります。また、彼女の内面的な成長も顕著で、愛や友情の重要性を理解し、他者との絆を深めることに成功します。
未来への展望
マインは自らの成長を通じて、未来に向けた希望を持つようになります。彼女の物語は、自己実現のための他者との関係の重要性を強調し、成長の過程で得た知識や経験が彼女をより強く、より優れた人物にしていく様子が描かれています。
整理してみると、マインの成長物語はよく練られたプロットの上で進んでいるのがわかります。冒頭のマインと比較して最終話のマインは人間的に大きく成長しています。これはもちろん、成人として未熟な面を持っていた本須麗乃自身の成長と変化の軌跡でもあります。
”転生者マイン”に対する作者の認識は?
作者である香月美夜さんが以前SNSで、転生マインに関して次のようにコメントしていました。
麗乃の記憶や人格が前世として奥底にあり、新しく生まれることで前世を包み込むように、マインの意識が生まれ育っていく。本来ならば、経験を積むことでマインとしての人格や意識が厚みを帯びていくので、前世の記憶に今の自分が呑まれることはない。
けれど、マインは身食い。
熱に呑まれるたびに自分が熱に食べられるような感じがして、自意識が穴だらけになる。
普通ならば、マインとしての言動を積み重ねることで今世の自分を立て直していくのに、ほとんどベッドで寝ているだけ。接するのは家族だけ。新しい経験ができない。
このコメントは中国の読者からの「”マインは熱が出た時に既に死んでおり、麗乃がマインに取って代わった”と捉えるファンと”麗乃がマインに転生したが、5歳時に前世の記憶が蘇ったため、前世の記憶が現在の記憶を上書きし、マインは自分がマインではなく麗乃だと思うようになった”と捉えるファンがいるが、どちらが正しい認識なのか」という質問に対する回答で、後者の認識であることを明言しています。
>麗乃とマインが従来同一の魂を持ち、麗乃がマインに転生しましたが、5歳の時前世の記憶が蘇ったため、前世の記憶が現在の記憶を上書きし、マインは自分がマインではなく麗乃だと思うようになった。
原作を深く読み込んでいる方でしょうか。
作者としてはこちらの意識で書いています。— 香月美夜@本好きの下剋上 (@miyakazuki01) November 15, 2019
身食いによってマインは”自意識が穴だらけ”状態になっていたため、前世の記憶を包み込むことができず、マイン本来の人格や意識を持ち合わせたまま育つことができなかった、という状態だったようです。
そういう認識の下で作品を読むと、転生マインの言動に対する理解度が高まるような気がします。
おわりに
物理的な健康問題、環境の制約、社会的な障壁、経済的な困難、人間関係の複雑さなどを乗り越え、転生直後には想像しえなかった幸せを掴んだマインは、下剋上をやり遂げたと言えるかもしれません。『本好きの下剋上』はその物語の作り込みやキャラクターの設定が秀逸であるがために、人間が抱えがちな欠点までリアルに浮き彫りにしてしまっている感があります。
読者の間でマインについていろいろな意見が交わされるのは、それだけこの作品がよく練られて作られている証だと考えられます。